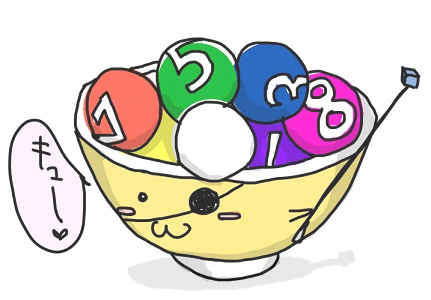澄んで、青く。花薫る。 23
「そう言えば、保健室の中ってどんな風になってるんだっけ?」
食堂から戻る途中、保健室前を通りかかったので、何気なく京一郎は聞いてみた。
「ん?じゃあ入ってみる?」
「え、や特に用もないのに不審がられるよ」
「京一郎、こないだ俺の話聞いてた?ここは特に用のない連中の溜まり場なんだってば。」
乙若が引き戸に手をかけると、内側から勢いよく戸が開いた。
「わ!・・・なんだ。柊先輩じゃん。」
中にいたのは、中等部生の制服を着た少年。伊勢薫だ。
「あ、こんにちは。」
「保健室に用?スメラギ先生だったら今日はいないよ。」
親切に教えてくれる。と、すかさず乙若が会話に割り込んできた。
「君、中等部生の伊勢薫くんだよね。奇遇だなぁ。僕は高等部1年の乙若。ちょっと教えて欲しいことがあるんだけど、いいかな?」
知らない先輩に急に話しかけられたせいか、不安そうな顔になって、薫は後退りする。その顔の横に、同じ顔がひょっこり現れて、乙若を冷たく見据えた。
「弟に何の用でしょう。」
これは薫の双子の兄の、馨だ。弟を守るように後ろに追いやる。
「まぁまぁ、警戒しないでよ。俺が聞きたいのは、生徒会のことなんだ。」
乙若の横で、京一郎も薫を見ながら頷く。
しかし、馨は取り合う気もないらしい。
「であれば、高等部の方に聞けばいいのでは。僕達は高等部生徒会役員ではないので。」
京一郎が初めて生徒会室に行ったとき、中等部生である彼らが部屋にいることを不思議に思ったものだったが、やはり役員ではなかったのだ。
「うーん。じゃあ、そんな君たちは、何で中等部じゃなくて、ここの保健室にいるのかな?」
「答える義務はないと思いますが。」
「困ったな。本当に知りたいのは君たちのことじゃないんだよね。」
そう言って乙若は京一郎に目配せしてくる。見上げる薫の視線が痛い。
「わかった。じゃあ俺が知ってることを話そうか。」
双子はますます怪訝そうに顔を見合わせる。
「薫くんはもともと体調の件と、心理的ストレスにより、中等部の保健室によく行っていた。しかし、担当していた養護教諭が高等部に異動になった。」
すらすらと述べ立てる乙若。薫の顔が青ざめてゆく。
「新しい養護教諭に馴染まなかった薫くんは、慣れ親しんだ養護教諭のいる高等部の保健室によく来ている。ついでに仲のいい先輩がいるから、よく生徒会室にも顔を出してる。因みに心身共に不安定な理由はーー」
「そこまで知ってるなら、僕らに聞くことなどないでしょう。」
怒りを露わにして、馨は乙若を睨みつける。
「君たちのことがどうこうっていうんじゃないさ。それより生徒会のことについて、役員には直接聞きづらいから、君たちにどうしても協力して欲しいんだ。ダメ?」
口元に微笑を湛えながら目が笑っていない乙若は、どこまで知られているか分からない不安をカードに、情報を引き出そうという魂胆らしい。らしくなく強引だ。
馨は相変わらず固い表情を崩さない。
「ね、ねえ、こんなところで立ち話もなんだからさ、とりあえず中庭のベンチに行かない?なんか奢るよ。」
場の雰囲気に居たたまれなくなった京一郎は、一先ず喫茶を提案してみる。意外にもこれに薫が食いついた。
「ジュース?!」
「あ、うん、ジュースとか、どうかな?」
「こら、薫!」
馨が兄の顔になって嗜める。
「柊先輩が奢ってくれるの?自販機のなら、何でもいい?」
「いいよ。好きなの選びなよ。」
乙若が小声で、京一郎ナイス、と囁く。
「薫、モノに吊られるなといつも言っているだろう。何をされるか分からない。戻るぞ。」
飲み物作戦に落ちるまであと一息の薫に対し、馨はますます不信の色を強めて弟を連れ戻そうとする。
しかし、薫が援護射撃してくれた。
「兄さま、柊先輩はそういう人じゃないよぉ。こないだだって助けてくれたし。たまにはこっちが助けてあげたっていいんじゃない?」
「薫くん・・・」
「薫、それとこれとは・・・」
「それに、ジュースだって奢ってくれるって言うんだしさぁ。兄さまだって、ビリヤ丼が出るファン太、高等部校舎の中庭にしかないの、知ってるでしょ?」
「う・・・」
ビリヤ丼とは、ビリヤードの球を丼に盛った形の、ゆるキャラである。期間限定で、特定の清涼飲料水のオマケのストラップになっているが、他のキャラクターと比べて当たる確率が低く、密かにコレクターの間で話題になっている・・・らしい。中等部の自販機には現在、その清涼飲料水が入っていないのだそうだ。さすがの彼らも、大手を振って高等部の中庭に入るのは気が引けるらしい。
「分かった。じゃあ僕もファン太買うから、もし当たったらあげるよ。」
「本当!?わーい!ほら、やっぱり柊先輩はいい人だ。」
うまく薫を乗せて、中庭へ向かう。
「僕らを侮辱するような真似をしたら、許しませんからね。」
乙若と京一郎を鋭く睨みながら、馨も渋々ついてくる。
めいめい、京一郎奢りの飲み物を手にベンチに座ったところで、乙若は口を開いた。
「ところでさ、二人は"千家副会長"の怪我のこと、知ってるんだよね?」
ぎくりとした様子で、二人とも目を逸らす。
「やっぱりね。ねぇ、君たちは変だと思わない?生徒会長が襲われるかもしれないからって、予め副会長に暴行させるって、正気を疑うよ。」
「柊先輩、他言無用とあれだけ・・・」
京一郎を睨みつける馨を乙若の強い声が遮る。
「さっき分かってくれたと思うけど、俺は情報収集にちょっと自信があるんだ。これは京一郎から聞いたわけじゃない。」
しれっと言う。京一郎はこっそり苦笑した。
俯く馨と対照的に、薫はペットボトルを両手で握りしめて、乙若を見上げた。
「やっぱり、先輩も変だと思うんだ・・・」
「・・・薫くん、やっぱり、って?」
京一郎が促す。
「・・・あの計画を初めて聞いたとき、乙若先輩と同じように、僕も変だと思ったんだ。でも、館林先輩もみんなも、千家先輩だって何も言わなくて、だから、・・・」
乙若と京一郎は顔を見合わせる。生徒会関係者は皆、伊織の怪我を肯定していると思っていたが、少なくとも薫は違うようだ。
「ねぇ先輩、僕はどうしたらいいの?千家先輩が怪我してるのは、見ていて辛いし、可哀想だよ。スメラギくんが怪我しなくて済んでるのはいいけど、その代わりにいつもあの人は血を流してる・・・」
薫は澄んだ目で京一郎と乙若を見上げる。
「薫くん、君はそれを、生徒会の誰かに言ったことある?」
乙若が尋ねる。
「うん。でも、館林先輩もみんなも、ほかにいい策がないって。」
「馨くんは、薫くんの意見について、どう思ってるのかい?」
京一郎は、威勢を削られて黙りがちな馨に振ってみる。
「それは、弟の言う通りだと思いますが、・・・僕らは生徒会役員でも、まして高等部生でもないので、口を出す筋合いがないし・・・」
馨は遠慮がちに呟く。
生徒会役員たちと、彼らの違いは何だろう。
高等部生であること、中等部生であること。しかしそれが決定的な要因だとは思えない。なぜなら、薫は高等部の保健室に頻繁に出入りしていて、スメラギ教諭の影響下にある筈なのだから。
「薫くんは、スメラギ先生に診てもらって、長いんだよね?」
念のため聞いてみると、薫は首を振った。
「ううん。僕の担当はスメラギ先生じゃなくて、おばちゃんだよ。それになんだか、スメラギ先生は怖いし・・・。」
おばちゃん、というのは、スメラギ教諭の他にもう一人居る養護教諭のことだろうか。
「中等部から異動してきた先生って、スメラギ先生のことじゃなかったんだ・・・」
「正直僕らはあの人が苦手なので、あの人がいる時にはあまり保健室や生徒会室には行きません。もちろん、緊急時は別ですけど。」
「苦手、か。ミサキ先生もそう言ってたな。俺は結構いいなーと思ったけど、どこら辺をそう思うの?」
薫は不安そうに視線を彷徨わす。
「先輩は、何とも思わないんだ?あの香水の匂い・・・。」
「香水?」
「スメラギ先生のつけてる香水は、薫の具合を悪くするんです。だから、僕らはスメラギ先生に出来るだけ近づかないようにしています。」
「最近は、生徒会室もちょっとあの匂いがしてて、だから行きづらい・・・。」
京一郎の記憶にある保健室は、入学後間もない頃、体育の授業中に倒れた伊織を見にいった時と、健康診断の時くらいだが、香水の匂いなどしていただろうか?
しかし、乙若の表情は険しくなった。
「二人とも、これからもスメラギ先生には近づかない方がいいかもしれない。もちろん、俺も、京一郎も。出来れば生徒会役員も。」
「香水が何かまずいの?」
「俺の勘が合ってればね。薫くん、馨くん、千家さんが生贄になる時、主導的に動いてるのは誰?」
「・・・館林先輩です」
馨の回答に、やっぱり、と呟くと、乙若は固い表情のまま言った。
「館林さんと放課後会えるように、取り計らってもらえないかな?」